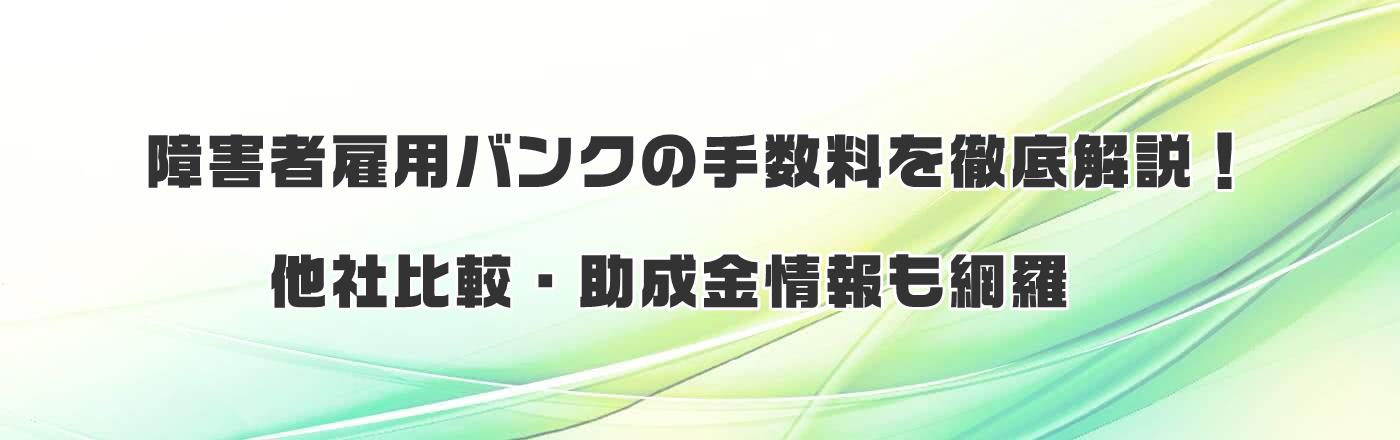
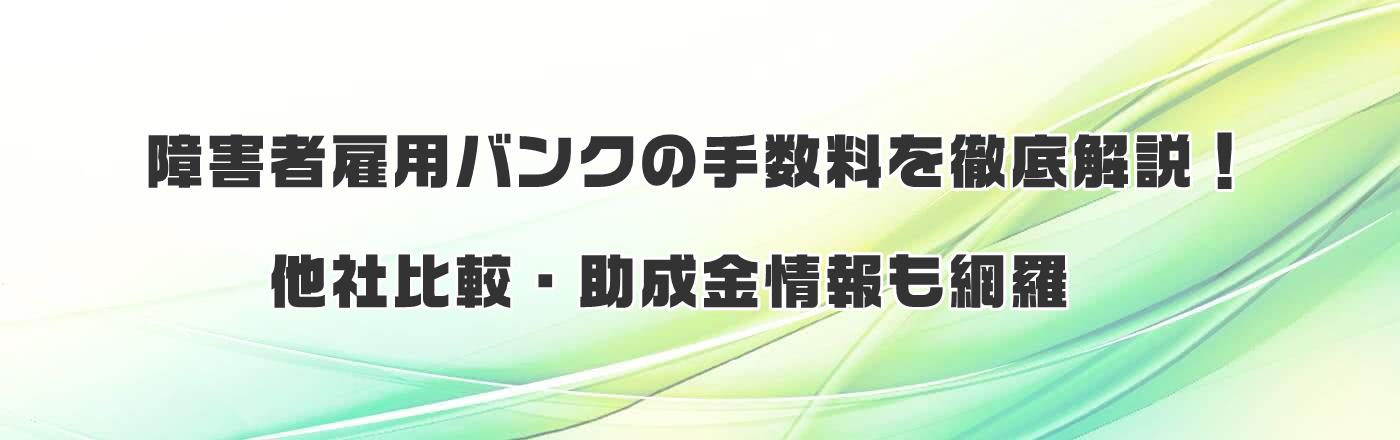
ーこのページにはPRリンクが含まれています。ー
この記事では、
- 「障害者雇用バンクって実際どうなの?手数料は高いのかな?」
といった疑問をお持ちの方に最適な内容となっています。

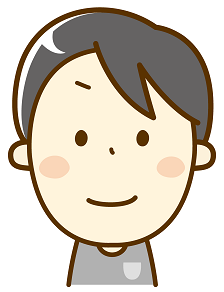
記事を読む時間がない方にむけて、結論を先に紹介しておきます。
障害者雇用バンクの利用は、求職者は完全に無料です。これは日本の法律(職業安定法)で定められているためです。
一方、企業が人材紹介サービスを利用する場合は、採用した人材の理論年収の35%程度が成功報酬として発生します。これは業界標準的な水準です。
その他、月額制のサテライトオフィスサービスもあります。企業はハローワーク(無料)やNPO、助成金制度の活用も併せて検討すると良いでしょう。
「障害者雇用バンクの手数料っていくらかかるんだろう?」
「他の転職エージェントと比べてどうなの?」
「企業側は費用がかかるって聞いたけど、求職者は本当に無料?」
障害者の就職・転職活動や、企業の障害者雇用において、「障害者雇用バンク」は非常に気になる存在ですよね。
特に「手数料」については、利用する上で最も重要な情報の一つです。
この記事では、世界的に有名なプロのコンテンツライターである私が、「障害者雇用バンク 手数料」と検索するあなたの疑問に、事実に基づいて徹底的にお答えします。
求職者の方も、企業の人事担当者の方も、この記事を読めば、障害者雇用バンクの手数料体系はもちろん、主要な転職エージェントとの比較、公的支援、さらには活用できる助成金制度まで、必要な情報をすべて理解できます。
専門用語も分かりやすく解説しながら進めますので、安心して読み進めてください。
障害者雇用バンクとは?
まずは、障害者雇用バンクがどのようなサービスなのか、基本情報から確認しましょう。
運営会社とサービス内容
障害者雇用バンクは、「株式会社HANDICAP CLOUD」によって運営されています。
約4万人が登録する、日本最大級の障害者向け総合求人サイトであり、転職エージェントサービスも提供しています。
求職者と企業の最適なマッチングを目指し、求人検索、就労支援情報の提供、ハローワーク求人の掲載、オンラインサポートなど、多岐にわたるサービスを展開しています。
特に、企業の規模や採用状況に応じた柔軟なサポートが強みです。
主な特徴と評判
最大の特徴は、企業求人、ハローワーク求人、そして就労移行支援事業所などの支援施設情報を、一つのプラットフォームでまとめて検索できる点です。
これは、求職者にとって非常に便利な機能と言えるでしょう。
さらに、採用後の定着をサポートするための「体調・業務・人間関係確認シート」や「障害配慮確認シート」といったツールも提供しており、入社後も見据えた支援体制が整っています。
利用者からは、「求人数が多い」「他のエージェントやハローワークの案件も見られて便利」「ウェブ面談に対応しているのが良い」といった声が上がっています。
障害者手帳を持っていれば、基本的に登録を断られることがないため、幅広い方が利用しやすい点も評価されています。
一方で、「連絡が遅いことがある」「個人情報の扱いに少し不安を感じる」といった意見も散見されますが、これらは他のエージェントサービスでも聞かれることがある一般的な課題とも言えます。
運営会社の規模は大手と比較すると小さいかもしれませんが、サービスの対応はしっかりしているという評価もあります。
障害者雇用バンクの手数料体系
さて、いよいよ本題の「手数料」について詳しく見ていきましょう。
求職者側と企業側、それぞれの視点から解説します。
求職者は完全無料!その理由とは?
結論から言うと、求職者の方が障害者雇用バンクを利用する際に、登録料や紹介料などの手数料を支払う必要は一切ありません。
これは、日本の「職業安定法」という法律で、原則として職業紹介事業者が求職者から手数料を徴収することを禁止しているためです。
これは障害者雇用バンクに限った話ではなく、認可を受けて運営しているほとんどの人材紹介会社(転職エージェント)に共通するルールです。
そのため、求職者の方は経済的な心配をすることなく、安心して就職・転職活動のサポートを受けることができます。
では、どうやって運営しているのか?
それは、企業側から手数料を得るビジネスモデルになっているからです。
企業向けの手数料
企業が障害者雇用バンクを利用する場合、主に2つのサービスで費用が発生します。
人材紹介サービス(成功報酬型)
最も一般的なのが、人材紹介サービスです。
これは「成功報酬型」という料金体系を採用しています。
成功報酬型とは?
求人を出したり、候補者を紹介してもらったりする段階では費用はかからず、実際に採用が決まった(成功した)時点で初めて費用が発生する仕組みです。
リスクを抑えて採用活動を進めたい企業にとっては、メリットの大きい料金体系と言えます。
障害者雇用バンクの標準的な手数料率は、採用が決まった人材の「理論年収」の35%とされています。
理論年収とは?
月給、賞与(ボーナス)、各種手当などを合算して計算される、その人が1年間働いた場合に得られると想定される年収のことです。
例えば、理論年収300万円の人材を採用した場合、300万円 × 35% = 105万円の手数料が発生します。
この35%という料率は、dodaなどの大手人材紹介サービスと同水準であり、業界の一般的な相場(30%〜35%)の範囲内です。
サテライトオフィス型雇用サービス
もう一つ、障害者雇用バンクは「サテライトオフィス型」の雇用サービスも提供しています。
こちらは月額制で、月額8万円から利用可能です。
サテライトオフィス型雇用とは?
企業が自社内に障害者雇用のための環境やノウハウがない場合に、専門のサポート体制が整った別の場所(サテライトオフィス)で、障害のある社員に働いてもらう雇用形態です。
管理やサポートはサテライトオフィス側が行うため、企業は雇用のハードルを下げることができます。
このサービスは、特に障害者雇用のノウハウが不足している企業にとって有効な選択肢となり得ます。
返金規定について
「もし採用した人がすぐに辞めてしまったら、手数料はどうなるの?」
これは企業にとって非常に気になる点ですよね。
多くの人材紹介サービスでは、採用した人材が一定期間内(例えば1ヶ月、3ヶ月など)に自己都合で退職した場合、支払った手数料の一部が返金される「返金規定」を設けています。
障害者雇用バンクの公式サイトなどからは、明確な返金規定の情報は見つかりませんでした。
しかし、業界標準を考えると、同様の規定が存在する可能性は高いです。
利用を検討する企業は、契約前に必ず返金規定の詳細を確認することが重要です。
表1:障害者雇用バンク:企業向け手数料概要
| サービス種類 | 手数料体系 | 具体的な料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介 | 成功報酬型 | 理論年収の35% (例:年収300万円の場合105万円) | 登録・掲載無料 |
| サテライトオフィス型雇用 | 月額固定 | 8万円〜/月 | 契約人数により変動 |
主要な転職エージェントとの手数料比較
障害者雇用に特化した転職エージェントは、障害者雇用バンク以外にもいくつかあります。
ここでは、代表的な「atGPエージェント」と「dodaチャレンジ」の手数料と比較してみましょう。
atGPエージェント (運営会社:株式会社ゼネラルパートナーズ)
求職者向け手数料:
もちろん無料です。
企業向け手数料:
こちらも成功報酬型ですが、手数料率は理論年収の最大50%と、障害者雇用バンクより高めの設定です。
また、特定のスキルを持つ人材を探す「スカウトサービス」などを利用する場合は、着手金(100万円)や活動費(1日5万円)が発生することもあります。
返金規定はしっかり設けられており、1ヶ月以内の退職で80%、3ヶ月以内で50%などが返金されます。
atGPは「やりがいのある仕事」や専門職に強く、高いスキルを持つ求職者に支持されています。
手数料率が高いのは、それだけ専門性の高い、あるいは採用が難しいポジションのマッチングに自信があることの表れかもしれません。
dodaチャレンジ (運営会社:パーソルダイバース株式会社)
求職者向け手数料:
こちらも無料です。
企業向け手数料:
dodaブランド全体としては、理論年収の35%を基準としています。
dodaチャレンジも、これに準ずる可能性が高いと考えられますが、契約時に確認が必要です。
初期費用は0円で、返金規定もあります(1ヶ月以内80%、3ヶ月以内50%など)。
dodaチャレンジは利用者満足度が非常に高く、きめ細かいサポートや非公開求人の多さが魅力です。
障害のある社員が多く在籍している点も、安心感につながっています。
比較のポイントと注意点
障害者雇用バンクやdodaチャレンジの35%は、市場の標準的な水準です。
atGPの最大50%は、プレミアムなサービス提供を目指す戦略と言えるでしょう。
企業側は、手数料率だけでなく、「理論年収」の計算方法にも注意が必要です。
賞与や手当の含め方によって、同じ料率でも実質的な手数料が変わってくるため、契約時に詳細を確認しましょう。
また、返金規定はリスク管理の上で非常に重要なので、必ずチェックしてください。
表2:主要転職エージェント:企業向け手数料比較
| エージェント名 | 運営会社 | 主な手数料率 (成功報酬) | 初期費用/その他費用 | 返金規定概要 |
|---|---|---|---|---|
| 障害者雇用バンク | (株)HANDICAP CLOUD | 理論年収の35% | 登録・掲載無料 | 詳細要確認 |
| atGPエージェント | (株)ゼネラルパートナーズ | 理論年収の最大50% | 特定探索サービス等で着手金・活動費あり | 有 (1ヶ月80%, 3ヶ月50%など) |
| dodaチャレンジ | パーソルダイバース(株) | (推定)理論年収の35% | 初期費用0円 | 有 (1ヶ月80%, 3ヶ月50%など) |
公的機関・NPO法人による支援と費用
民間の転職エージェントだけでなく、公的な機関やNPO法人も、障害者の就職を力強くサポートしています。
これらは費用面で大きなメリットがあります。
ハローワークの障害者専門窓口
ハローワーク(公共職業安定所)には、障害のある方向けの専門窓口があり、求人紹介やカウンセリング、面接対策などを無料で受けることができます。
企業側も無料で求人を掲載できます。
地域密着型の求人が多く、無料で利用できる点は大きな魅力です。
しかし、「求人の質にばらつきがある」「職員によって対応が違う」「民間エージェントほど手厚いサポートは期待できない」といった声もあります。
無料であることのメリットと、サービスの質とのバランスを考える必要があります。
NPO法人による就職支援
多くのNPO法人が、障害者向けの就労支援を行っています。
特に「就労移行支援」というサービスでは、利用者は世帯収入に応じて自己負担額が決まりますが、多くの場合無料または非常に低い負担で、職業訓練や就職サポートを受けられます。
企業向けには、NPO法人が有料職業紹介を行っているケースもあります。
例えば、認定NPO法人Switchでは、成功報酬として年収の20%という、民間エージェントより低い手数料率を設定しています。
NPO法人は、特定の障害への深い理解や地域との連携を強みとしている場合が多く、企業にとって費用対効果の高い選択肢となる可能性があります。
表3:NPO法人による職業紹介:企業向け費用例
| NPO法人例 | 手数料体系 | 具体的な料金 | 返金規定 |
|---|---|---|---|
| 認定NPO法人Switch | 成功報酬型 | 年収の20%、求人受理時事務費用1,000円 | 有 (3ヶ月以内50%, 6ヶ月以内30%) |
| (参考) (株)エンカレッジ | 月額制 | 社員1名につき月額5万円〜 | 要確認 |
企業が活用できる助成金制度
企業が障害者を雇用する際には、国から様々な助成金を受けられる可能性があります。
これを知っているか知らないかで、コスト負担は大きく変わります。
主な助成金の種類
代表的なものに「特定求職者雇用開発助成金」があります。
これは、障害者など就職が困難な方を雇用した事業主に支給されるもので、数十万円から数百万円になることもあります。
他にも、「トライアル雇用助成金」や「キャリアアップ助成金」など、様々な制度があります。
民間エージェント利用と助成金
ここで重要なポイントです。
「特定求職者雇用開発助成金」などは、ハローワーク経由だけでなく、一定の基準を満たした民間の職業紹介事業者(障害者雇用バンクなども含まれる可能性があります)を通じて採用した場合でも、受給できる場合があります。
つまり、有料の民間エージェントを利用して高い質の採用を目指しつつ、助成金でその費用の一部を補う、という戦略が可能なのです。
これにより、企業は実質的な負担を抑えながら、最適な人材を確保しやすくなります。
ただし、助成金の申請には複雑な条件や手続きが伴うため、厚生労働省の最新情報を確認し、利用するエージェントが助成金の対象となるかを確認することが不可欠です。
表4:障害者雇用関連助成金:民間紹介利用時のポイント
| 助成金名 | 民間紹介利用時の適用 | 主な条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金 (各種コース) | 可 | 厚労省指定基準を満たす紹介事業者経由、継続雇用、紹介前の選考不可、関連解雇なしなど | 申請手続き煩雑 |
| トライアル雇用助成金 | 主にハローワーク経由だが、個別ケースは確認要 | - | - |
まとめ:最適なサービスを選ぶためのポイント
ここまで、障害者雇用バンクの手数料を中心に、様々なサービスとその費用について見てきました。
最後に、求職者と企業のそれぞれにとって、どのようにサービスを選べば良いのか、ポイントをまとめます。
各サービスの費用対効果
- 民間エージェント(障害者雇用バンクなど):企業には費用がかかるが、専門的なサポートと質の高いマッチングが期待でき、助成金活用で費用対効果を高められる可能性あり。求職者は無料。
- ハローワーク:完全無料が最大のメリット。ただし、サポートの質にはばらつきがある可能性も。
- NPO法人:求職者は訓練を低負担で受けられる。企業は低コストで紹介を受けられる可能性あり。
求職者向けの選択ポイント
求職者の方は、どのサービスも基本的に無料で利用できます。
そのため、サービスの質、求人の種類、サポート体制を基準に選びましょう。
一つのサービスに絞らず、複数のサービス(例えば、民間エージェント1社+ハローワーク)に登録するのがおすすめです。
自分の希望や障害特性、求めるサポート内容をカウンセラーにしっかり伝え、自分に合ったサービスを見つけましょう。
企業向けの選択ポイント
企業の方は、費用と質のバランスが重要です。
求める人材の専門性や緊急度に応じて、民間エージェントとハローワーク・NPOを使い分けましょう。
助成金の活用は必ず検討してください。
民間エージェントを利用する場合は、手数料率、理論年収の定義、そして返金規定を契約前に必ず書面で確認することが鉄則です。
採用後の定着支援も視野に入れ、長期的な視点でサービスを選びましょう。
この記事が、「障害者雇用バンク 手数料」について調べているあなたの疑問を解消し、より良い就職・転職活動、そして企業の採用活動の一助となれば幸いです。
